久しぶりに今日はちょっと真面目な投稿。
最近読んだ雨宮処凛さんの記事に、とても考えさせられました。
テーマは「昭和ノスタルジー」。
記事を読みながら、正直なところ「わかる」と頷いてしまった自分がいました。
昭和ノスタルジーへの共感
もちろん、昭和が絶対的に良かったと言いたいわけではありません。
性別役割の固定やパワハラ・セクハラが当たり前の社会なんて、もうごめんです。
それでも、「今日より明日は豊かになる」と信じられた時代への羨望は確かにあります。
父親の給料だけで家族が暮らし、子どもが教育を受けられる社会。
努力すればある程度は報われる、そんな安心感。
今のように「競争に勝ち続けなければ転落する」という自己責任社会と比べると、あの時代の希望や期待に惹かれる部分があるのは否めません。
支持基盤は“真ん中=ロウアーミドル層”
記事では「真ん中」にいる人々――大企業の正社員でもなく、かといって極端な貧困層でもない人々――が、参政党の支持基盤になっていると指摘されていました。
非正規や低賃金で暮らし、貯金もほとんどなく、結婚や家庭を持つことも難しい。
それでも「弱者」とは認められず、支援からも漏れ、「自己責任」で放置されてきた層です。
この人たちの素朴な不安に、「日本人ファースト」や「昭和回帰」といった言葉が強く響いてしまう。
記事を読んで、その構図が腑に落ちました。
マイノリティ支援の極端さ
リベラル派がマイノリティ支援に偏りすぎている、という指摘にも考えさせられました。
LGBTQ当事者として、LGBTQや障害者、高齢者などが「社会的弱者」として守られるのは当然だと考えています。
けれど、それは決して“特別な権利”ではありません。
残念なのは、その隔たりのせいで枠組みから外れた“普通の人”が見過ごされがちになってしまっていることです。
「誰が弱者なのか」を決めつけ、そこに入らない人を切り捨てるような姿勢は、結果的に“真ん中”をさらに不安に追い込んでいるではないか。
そう考えると、昭和ノスタルジーへの共感は単なる懐古趣味ではなく、現代社会のひずみの裏返しなのかもしれません。
まとめ
昭和的な価値観を美化したいわけではありません。
けれど、あの時代の「安心感」や「希望」に惹かれる気持ちは確かに理解できます。
その背景にあるのは、“真ん中”で必死に生きてきた人たちの疲弊と不安。
この記事は、そのことをとても鮮やかに言語化してくれたと思いました。

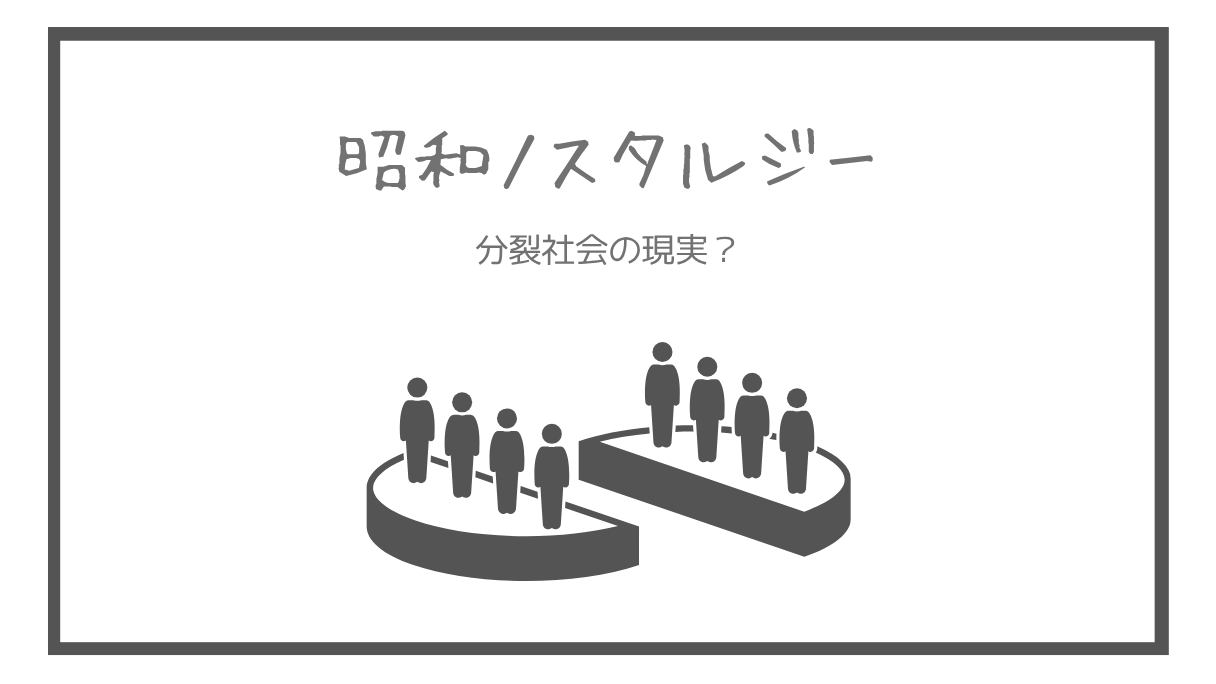





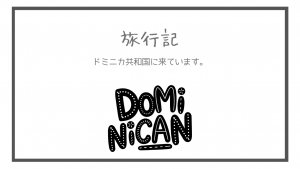




コメント
コメント一覧 (2件)
多分私もこの「真ん中の人」枠。
それでも私がまだ極端な思考側に行って無いのは、
人生いつも日本社会の潮流の半歩外側で生きてきた
から(生きざるをえなかった?)かなとも思ったり。
今や半歩では済まない距離でプカプカ浮いてますけど(笑)
Giroさん、こんにちは〜❣️
今日もコメント有難うございます❤️
同感。
生きざるを得なかったが正しいですよね。
それでも海外に来て日本を外から見るようになると日本では想像もしなかった事を感じさせられる事ありますよね。
自分は何だかんだ言っても日本好きだったんだなって思い知っています。